ここから本文です。
みなとへGO! 横浜港の歴史(5)
最終更新日 2024年7月31日
![]() 横浜港の歴史(一般の方向け)
横浜港の歴史(一般の方向け)![]() 開港 ~ 文明開化
開港 ~ 文明開化 ![]() 市制施行 ~ 関東大震災
市制施行 ~ 関東大震災 ![]() 震災復興 ~ 第二次世界大戦
震災復興 ~ 第二次世界大戦![]() 戦後 ~ 高度経済成長期
戦後 ~ 高度経済成長期 ![]() コンテナ時代 ~ 現在
コンテナ時代 ~ 現在
5.コンテナ時代~現在
1974年~
昭和49年~

みなとみらい21を望む
高度経済成長という日本経済のはげしい変化は、近代化、合理化の波となって、港にも大きな影響をもたらしました。
1967年(昭和42年)ごろから、外国貨物の輸送に「コンテナ」という鉄製の大きな箱が使われるようになったのです。
それまで、多くの貨物は、個々にこん包され1つ1つ船に積まれていたので、包装、船積みや荷下ろしのための荷役作業、港から港までの輸送などに、たいへんな時間と人手と費用がかかっていました。
ところが、「コンテナ」を使うと、貨物の包装は簡単になり、荷役作業はガントリークレーンとよばれる大型クレーンによって短時間で大量にできるようになり、さらに、受取人ごとの貨物の整理が簡単なため、港から港への輸送もたいへん速く、しかも楽になりました。
また、「コンテナ」による貨物の輸送は、安全性も高くなりました。
コンテナ貨物の量は、年ごとにたいへんな勢いでふえ続けています。
コンテナを専用に運ぶ「コンテナ船」が登場し、船の大型化が進んでいます。
しかし、それまでの横浜港の施設は、すべて昔からの一般貨物船用に建設されていたので、これらの施設でもコンテナ荷役はできますが、効率がよくないためコンテナ船用の港湾施設を急いで建設しなければなりませんでした。
そこで、横浜市では、コンテナ貨物を取り扱うための港湾計画をたて、まず、本牧ふ頭や大黒ふ頭を建設し、「ガントリークレーン」を据え付けるなどして、コンテナ貨物用の施設を整えました。
しかし、さらに増加するコンテナ貨物に対応するため、1991年(平成3年)から南本牧ふ頭の建設を始め、2001年(平成13年)には4つのコンテナターミナル計画のうち、2つのターミナルを、2015年には3つ目のターミナルをオープンしました。
このように、明治時代の中頃から始まった整備によって、港は沖側へ拡がっていきましたが、開港から150年を経た現在、山内ふ頭・高島ふ頭から新港ふ頭・大さん橋地区は港の一番奥まったところになり、老朽化も進みました。
そのため港とまちの調和をはかり、新しい横浜のウォーターフロントをつくり出す「みなとみらい21計画」「大さん橋ふ頭再整備事業」などが進められました。
また港には欠くことのできない臨港道路をはじめ、市民に親しまれる港とするため、帆船日本丸・横浜みなと博物館、赤レンガ倉庫、臨港パーク、象の鼻パーク、海の公園、八景島、海づり施設などが整備され利用されています。

フルコンテナ船第一船サンファン号(写真/横浜みなと博物館所蔵)
「この時代の主な輸入品」
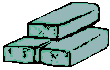
非鉄金属(ひてつきんぞく)

自動車(じどうしゃ)
「この時代の主な輸出品」

事務用機器(じむようきき)

自動車(じどうしゃ)
このページへのお問合せ
港湾局政策調整部政策調整課
電話:045-671-7165
電話:045-671-7165
ファクス:045-671-7310
メールアドレス:kw-seisaku@city.yokohama.lg.jp
ページID:657-601-370







