ここから本文です。
みなとへGO! 横浜港の歴史(2)
最終更新日 2024年7月31日
![]() 横浜港の歴史(一般の方向け)
横浜港の歴史(一般の方向け)![]() 開港 ~ 文明開化
開港 ~ 文明開化 ![]() 市制施行 ~ 関東大震災
市制施行 ~ 関東大震災 ![]() 震災復興 ~ 第二次世界大戦
震災復興 ~ 第二次世界大戦![]() 戦後 ~ 高度経済成長期
戦後 ~ 高度経済成長期 ![]() コンテナ時代 ~ 現在
コンテナ時代 ~ 現在
2.市政施行~関東大震災
1889年~1923年
明治22年~大正12年
政府は、1889年(明治22年)から何回にもわたって港の建設工事をして、近代的な港にするように努めたので、横浜港はわが国第一の国際貿易港として日本の表玄関になり、貿易額は年ごとにふえていきました。
客船ふ頭としていまでも親しまれている大さん橋ふ頭や東・北水堤(内防波堤)は1889年(明治22年)から1896年(明治29年)にかけて、また、赤レンガ倉庫で知られる新港ふ頭は1899年(明治32年)から1916年(大正5年)にかけて建設されました。
新港ふ頭では、当時の施設の一部が今でも利用されています。
さらにこの頃、海に面した土地に工場が建つようになり、川崎から神奈川にかけての遠浅海岸は、多くは、民間により工場用地として埋め立てられ、京浜工業地帯がつくられましたが、1923年(大正12年)9月1日の関東大震災で、開港以来築かれてきた横浜港の施設は、ほとんど壊されてしまいました。
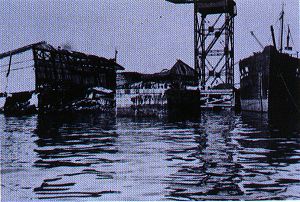
関東大震災時の新港ふ頭(写真/横浜みなと博物館所蔵)
「この時代の主な輸入品」

繰綿(くりわた)

羊毛(ようもう)
「この時代の主な輸出品」

生糸(きいと)
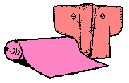
羽二重(はぶたえ)
このページへのお問合せ
港湾局政策調整部政策調整課
電話:045-671-7165
電話:045-671-7165
ファクス:045-671-7310
メールアドレス:kw-seisaku@city.yokohama.lg.jp
ページID:893-492-967







