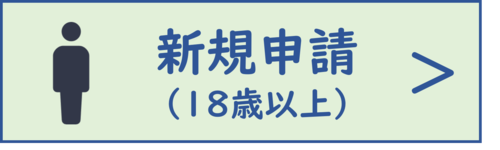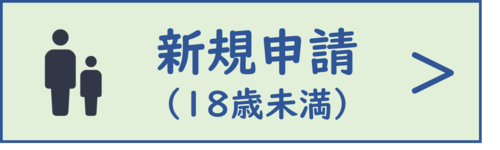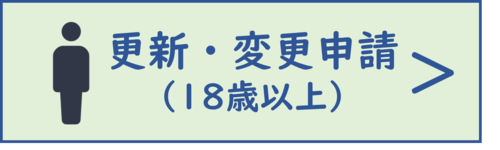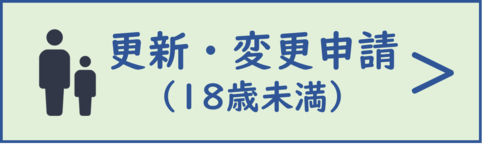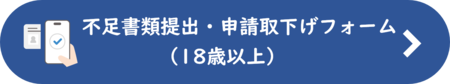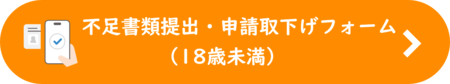ここから本文です。
オンライン申請について-障害福祉サービス-
最終更新日 2025年4月23日
-目次
申請の準備(はじめにお読みください)
横浜市では令和7年2月から障害福祉サービスに係る一部の手続きのオンライン申請を開始しました。
※オンライン申請とは、スマートフォンやパソコンで行う申請のことをいいます。
要件
| 要件 | 備考 |
|---|---|
①マイナンバーカードを持っていて、マイナポータルにログインできる環境にある |
申請に当たっては |
| ➁利用者本人である | 利用者が18歳未満の場合は保護者 |
| ③右のいずれかの申請である | 障害福祉サービスに係る以下の申請
|
手続き一覧
障害福祉サービスについてお知りになりたい方は、障害福祉サービスの概要(横浜市ホームページ)をご覧ください。
※補装具・日常生活用具・コミュニケーション支援は、オンライン申請の対象外です。
| 手続き | 対象者 | 注意事項 |
|---|---|---|
1. |
横浜市で初めて障害福祉サービスをしたい方 |
|
2. |
既に横浜市の受給者証をお持ちの方で、障害支援区分の更新を行いたい方 |
|
3. |
既に横浜市の受給者証をお持ちの方で、サービスの継続利用やサービスの追加、日数・時間・回数の変更を希望する方 |
|
以下の場合はオンラインで申請することはできません。区役所窓口で申請してください。
- 市外転出・市内区間異動・死亡による支給期間中途のサービス終了
- 計画相談事業所やモニタリング期間の変更
- 上限額管理事業所の登録・変更
- 受給者証の返還
- 代理人による申請(家族含む ※利用者が18歳未満の場合の保護者を除く)
必要書類一覧
新規申請、サービスの更新申請など、利用者負担の判定が必要な申請については、添付資料が必要です。
以下の対象者に該当する場合は添付書類を提出してください。
※課税年度:サービスの利用開始予定月が1~6月の場合は前年、7~12月の場合は現年が課税年度となります。
例:令和7年3月にサービスの利用開始予定 → 課税年度は令和6年度のため、令和5年1月~12月の収入等に係る書類を提出
令和7年7月にサービスの利用開始予定 → 課税年度は令和7年度のため、令和6年1月~12月の収入等に係る書類を提出
| 対象者 | 添付書類(申請時に画像データ等を添付してください) | |
|---|---|---|
| 20歳以上の市民税非課税世帯の方で、施設入所または療養介護のサービスを利用する方 | 年金の受給者 | 課税年度(※)の前年1月から12月までの振込金額が分かるもの 【例】
※1月から12月までの振込金額を確認するため、年金額改定通知書や年金振込通知書を提出する場合は、2年度分添付してください。 |
年金生活者支援給付金の受給者 ※年金生活者支援給付金は、障害基礎年金を受給している人で、前年の所得が一定金額以下の場合に、年金に上乗せして受け取ることができる給付金です。 | 課税年度(※)の前年1月から12月までの振込金額が分かるもの 【例】
| |
| 手当の受給者 | 課税年度(※)の前年1月から12月までの振込金額が分かるもの 【例】
| |
| 工賃収入がある人 | ※障害福祉サービス事業所等に記入してもらったものをスキャンまたは撮影し、添付してください。 ※障害福祉サービス事業所等が独自に作成している様式でも可 | |
税金を支払っている人 【注意】未申告の方は、必ずお住まいの区役所税務課で税申告を行ってください。 | 課税年度(※)の前年1月から12月までの税額が分かる書類 | |
社会保険料を支払っている人 | 及び 課税年度(※)の前年1月から12月までの社会保険料の金額が分かる書類 | |
| 在日外国人障害者等福祉給付金や仕送り、不動産収入等の収入がある人 | 課税年度(※)の前年1月から12月までの収入が分かる書類 【例】
| |
| グループホーム(共同生活援助)の利用者 | 家賃が分かるもの 【例】
| |
| 療養介護の利用者 | 食事療養費に係る減額認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証) 及び 【健康保険情報に変更がある場合のみ】健康保険被保険者証の記号及び番号や保険者名の分かるもの(有効期限内の保険証や資格確認書等) | |
| 18歳以下の人を扶養している人 | 源泉徴収票のコピー | |
手続の流れ
①事前相談
新たに障害福祉サービスの利用を希望する場合や現在利用している障害福祉サービスの支給量変更やサービス追加を希望する場合は、必ず事前にお住まいの区の福祉保健センター高齢・障害支援課(18歳未満の場合はこども家庭支援課)にご相談ください。
②オンライン申請
STEP1
マイナンバーカードを用意し、利用者証明用電子証明書のパスワード(4桁の数字)及び署名用電子証明書のパスワード(6~16桁の英数字)を確認します。
※パスワードを忘れたりロックされた場合は、以下のページをご覧ください。
Q.マイナンバーカード(電子証明書)の暗証番号を忘れたりロックした場合はどうすればいいですか
STEP2
各手続きの申請ページ(マイナポータル)にアクセスします。
STEP3
必要事項の入力や必要書類の添付を行います。
申請時にメールアドレスを入力すると、マイナポータルから自動返信のメールが届きます。横浜市からのお知らせを案内していますので、確実にメールが受信できるメールアドレスを入力してください。
・ドメイン指定受信を設定されている方は「@mail.oss.myna.go.jp」からのメールを受信できるように指定してください。
・マイナポータルからのメールは、メールアドレスを入力した際に1通、申請時に2通届きます。申請時(「電子署名して申請する」まで進んだ際)に届く「【マイナポータルぴったりサービス】電子申請受付のご連絡」という件名のメールが届いていれば、横浜市に申請が届いています。横浜市から別途申請を受け付けた旨の連絡は行いません。
STEP4
申請後、控えを必ずダウンロードしてください。
※後日、区福祉保健センターが申請内容を確認し、必要に応じて追加書類提出や面談等を行った上で、決定通知書及び受給者証が交付されます。
※申請(送信)した日時や申請内容は、ダウンロードしたデータで確認できます。ただし、添付書類はダウンロードできませんので、申請時に添付したデータはお手元に残してください。
③サービス等利用計画案の作成
区福祉保健センターよりサービス等利用計画案の作成を依頼します。
※障害福祉サービスの利用には、指定特定相談支援事業所等が作成する「サービス等利用計画案」の作成・提出が必要です。
相談支援事業所の相談支援専門員は障害福祉サービスの利用者・利用希望者に必要なサービスを確認してサービス等利用計画案を策定します。また、ご本人(ご家族・支援者を含む)がサービス等利用計画案を作成するセルフプランも認められています。
指定特定相談支援事業所の受入可能状況などの情報はこちら(市民のみなさま向け情報【計画相談支援】)
※介護保険サービスと障害福祉サービスの併用を希望される場合は、サービス等利用計画案の代わりに、ケアマネージャーが作成するケアプランをもとに支給決定を行います。詳しくは相談窓口までお問い合わせください。
④認定調査・障害支援区分の認定
申請先の区福祉保健センター職員が利用者の心身の状況を把握するため、調査を行います。
※「介護給付」または「訓練等給付のうち共同生活援助(入浴、排せつ又は食事等の介護を伴う場合)」の申請をする場合、障害支援区分が必要となります。
障害支援区分とは、障害特性と心身の状態に応じて、必要とされる標準的な支援の度合いを示す指標で、障害者手帳の等級とは異なる基準で審査・認定されます。
⑤支給決定
認定された障害支援区分や提出されたサービス等利用計画案に基づき区福祉保健センターで障害福祉サービスの支給決定が行われます。
支給決定が行われると、障害福祉サービスの受給者(18歳以上の場合は利用者本人、18歳未満の場合は利用者の保護者)に障害福祉サービス受給者証が発行されます。
⑥サービス提供事業所との契約・利用開始
サービス提供事業所と利用契約して、サービスを利用します。その際、障害福祉サービス受給者証をサービス提供事業所にご提示ください。
1.新規申請
横浜市で初めて障害福祉サービスを申請する場合の手続きです。
(1)オンラインで新規申請ができる方
マイナンバーカードを持っており、以下のいずれかに該当する方
- 身体障害者手帳をお持ちの方
- 愛の手帳(療育手帳)をお持ちの方
※知的障害があるが、愛の手帳をお持ちでない方は、お住まいの区役所までご相談ください。 - 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
※精神障害(発達障害含む)があるが、精神障害者保健福祉手帳をお持ちでない場合も、精神障害を事由として自立支援医療受給者証(精神通院医療)や年金等の給付を受けている方、医師の診断書がある方は申請できる場合があります。事前にお住まいの区役所までご相談ください。 - 難病疾患等(障害者総合支援法の対象疾病(外部サイト)に限る)で一定の障害のある方
※指定難病の要件とは異なります。
※申請を行う前に必ず、お住まいの区の福祉保健センター高齢・障害支援課(18歳未満の場合はこども家庭支援課)にご相談ください。
※オンライン申請は利用者本人(利用者が18歳未満の場合は保護者)のみ行うことができます。
(2)オンライン申請後の流れ(新規申請)
申請データは、申請先の区の福祉保健センター高齢・障害支援課(18歳未満の場合はこども家庭支援課)に届き、入力内容や添付書類について確認します(確認までに数日から1週間ほどかかります)。
- 申請した際(「電子署名して申請する」まで進んだ際)にメールで届く「【マイナポータルぴったりサービス】電子申請受付のご連絡」という件名のメールの本文(【横浜市からの大切なお知らせ】)に、申請後の手続きの流れや申請内容の変更方法などのご案内(PDFファイルへのリンク)が掲載されています。
- 申請内容や提出書類に不備や不足等があった場合は、福祉保健センターの担当から電話等で連絡させていただきます。
サービスの支給決定がされると、決定通知書及び障害福祉サービス受給者証を郵送等で交付します。
(3)オンライン申請入口
上記の内容をお読みいただいたうえで、以下の入口からオンライン申請を行ってください。
(4)注意事項
- 申請を行う前に必ず、お住まいの区の福祉保健センター高齢・障害支援課(18歳未満の場合はこども家庭支援課)や相談支援事業者に制度やサービスの利用についてご相談ください。
- サービスの利用にあたり区の福祉保健センター高齢・障害支援課(18歳未満の場合はこども家庭支援課)の職員との面接を行う必要があります。
2.区分更新申請
既に横浜市の受給者証をお持ちの方で、障害支援区分の更新を行う場合の手続きです。
※障害支援区分の期間内に障害福祉サービスの更新手続きを行う方は、3.更新・変更申請をご覧ください。
(1)オンラインで区分更新申請ができる方
マイナンバーカードを持っており、以下の全てに該当する方
- 受給者証(ピンク色)の交付を受けており、障害福祉サービスを利用している
- 障害支援区分の有効期間後も障害福祉サービスの利用を希望する(障害支援区分の有効期間終了前に区役所より申請のご案内が来ます。)
(2)オンライン申請後の流れ(区分更新申請)
申請データは、申請先の区の福祉保健センター高齢・障害支援課(18歳未満の場合はこども家庭支援課)に届き、入力内容や添付書類について確認の上、区分認定調査の調整をさせていただきます(確認までに数日から1週間ほどかかります)。
- 申請した際(「電子署名して申請する」まで進んだ際)にメールで届く「【マイナポータルぴったりサービス】電子申請受付のご連絡」という件名のメールの本文(【横浜市からの大切なお知らせ】)に、申請後の手続きの流れや申請内容の変更方法などのご案内(PDFファイルへのリンク)が掲載されています。
- 申請内容や提出書類に不備や不足等があった場合は、福祉保健センターの担当から電話等で連絡させていただきます。
調査実施後、サービスの支給決定がされると、決定通知書及び障害福祉サービス受給者証を郵送等で交付します。
(3)オンライン申請入口
上記の内容をお読みいただいたうえで、以下の入口からオンライン申請を行ってください。
(4)注意事項
- 支給量の変更を希望する場合は、申請前に必ず相談支援事業所かお住まいの区の福祉保健センター高齢・障害支援課(18歳未満の場合はこども家庭支援課)にご相談ください。
- 新たに利用を希望するサービスがある場合は、申請前に必ず相談支援事業所かお住まいの区の福祉保健センター高齢・障害支援課(18歳未満の場合はこども家庭支援課)にご相談ください。
3.更新・変更申請
既に横浜市の受給者証をお持ちで、サービスの継続利用やサービスの追加、日数・時間・回数の変更の申請をしたい場合の手続きです。
※障害支援区分の更新を行う場合には、2.区分更新申請をご覧ください。
(1)オンラインで更新・変更申請ができる方
マイナンバーカード及び受給者証(ピンク色)を持っており、以下のいずれかに該当する方
- 現在利用しているサービスを支給決定期間終了後も引き続き利用を希望している(支給決定期間終了前に区役所より申請の案内があります)
- 利用するサービスの追加を希望している(事前に区役所の地区担当職員に相談してください。)
- 利用しているサービスの日数・時間・回数の変更を希望している(事前に区役所の地区担当職員に相談してください。)
※計画相談事業所やモニタリング月の変更等、上記に該当しない変更手続については区役所窓口で手続きをお願いします。
※オンライン申請は利用者本人(利用者が18歳未満の場合は保護者)のみ行うことができます。
(2)オンライン申請後の流れ(更新・変更申請)
申請データは、申請先の区の福祉保健センター高齢・障害支援課(18歳未満の場合はこども家庭支援課)に届き、入力内容や添付書類について確認します(確認までに数日から1週間ほどかかります)。
- 申請した際(「電子署名して申請する」まで進んだ際)にメールで届く「【マイナポータルぴったりサービス】電子申請受付のご連絡」という件名のメールの本文(【横浜市からの大切なお知らせ】)に、申請後の手続きの流れや申請内容の変更方法などのご案内(PDFファイルへのリンク)が掲載されています。
- 申請内容や提出書類に不備や不足等があった場合は、福祉保健センターの担当から電話等で連絡させていただきます。
サービスの支給決定がされると、決定通知書及び障害福祉サービス受給者証を郵送等で交付します。
(3)オンライン申請入口
上記の内容をお読みいただいたうえで、以下の入口からオンライン申請を行ってください。
(4)注意事項
- 支給量の変更を希望する場合は、申請前に必ず相談支援事業所かお住まいの区の福祉保健センター高齢・障害支援課(18歳未満の場合はこども家庭支援課)にご相談ください。
- 新たに利用を希望するサービスがある場合は、申請前に必ず相談支援事業所かお住まいの区の福祉保健センター高齢・障害支援課(18歳未満の場合はこども家庭支援課)にご相談ください。
4.不足書類提出・申請取下げフォーム
申請の際に不足書類があった場合、オンラインで追加提出することができます。以下の不足書類提出・申請取下げフォームで必要事項を入力後、不足書類の画像データ等を添付して提出してください。
また、申請を取下げたい場合にも、以下の不足書類提出・申請取下げフォームをお使いいただけます。
※不足書類の提出にあたっては、マイナンバーカードは不要です。
※利用者本人以外の方の代理申請も可能です。
オンライン申請に関するお問い合わせ先
障害福祉サービスのオンライン申請に関する一般的なお問い合わせ
- 障害者福祉業務オンライン申請コールセンター
電話番号 0570-041294
FAX番号 045-550-4717
メールアドレス info@shogai-online.city.yokohama.lg.jp
受付時間 8時45分~17時15分(土日祝を除く)
障害福祉サービスの支給決定に関する相談
- 各区福祉保健センター 高齢・障害支援課またはこども家庭支援課
・18歳以上の障害者の方・・・高齢・障害支援課
・18歳未満の障害児の方・・・こども家庭支援課
連絡先は、各区の障害に関する相談窓口(横浜市ホームページ)でご確認ください。
マイナンバー制度に関する問い合わせ先
- マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178(平日9時30分~20時/土日祝9時30分~17時30分)
よくあるご質問
マイナポータルについて
オンライン申請には電子署名(公的個人認証)があるため、本人のマイナンバーカード(18歳未満の場合には保護者のマイナンバーカード)が必要です。オンライン申請を開始する前に、マイナンバーカードのパスワードをご確認ください。また、マイナポータルアプリをインストールする必要があります。
本申請においては、利用者本人のみがオンラインで申請可能です。
ただし、利用者が18歳未満の場合は保護者の方がオンラインで申請できます。
利用者が18歳以上の場合のご家族や法定代理人、施設の方等はオンラインでは申請できません。
※オンライン申請はマイナポータルが提供するサービスの一つである「ぴったりサービス」を使用して行います。
マイナポータルには代理人機能がありますが、使用可能なサービスが限定されており、本申請においては使用できません。
マイナポータルアプリに対応しているスマートフォンである必要があります。 対応可能機種(外部サイト)(外部サイト)
対応可能なスマートフォンをお持ちの方は、以下のリンクから注意事項等をお読みになり、マイナポータルアプリのインストールや利用者登録(初回のみ)を行ってください。
Androidの方(外部サイト)
iPhoneの方(外部サイト)
※なお、マイナンバーカードを携帯していなくても、スマートフォン一つでマイナポータルへのログインや各種行政手続き等が実施できる 「スマホ用電子証明書」についてはこの先のサイトで内容をご確認ください。(外部サイト)
対応機種一覧/iPhone未対応(外部サイト)
パソコンでオンライン申請をする場合、ICカードリーダライタを使ってログインする方法と二次元コードを使ってログインする方法の2種類あります。
★ICカードリーダライタを使ってログインする方法
ICカードリーダライタを用意する必要があります。(家電量販店等で購入できます。)
くわしくは ICカードリーダライタを使ってログイン(外部サイト) をご覧ください。
★二次元コードを使ってログインする方法
二次元コードログインに対応したスマートフォンを用意する必要があります。(スマートフォンを使って本人認証を行います。)
くわしくは 二次元コードを使ってログイン(外部サイト)をご覧ください。
※二次元コードを読み取る際は、マイナポータルアプリの「読取り」機能を使用します。
※通常のカメラアプリで読み取るとエラーになります。
・マイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取った際に、ご自身で設定した暗証番号のことです。
・電子証明書とは、信頼できる第三者(認証局)が間違いなく本人であることを電子的に証明するもので、書面取引における印鑑証明書に代わるものといえます。
・マイナンバーカードに記載されている電子証明書は、次の2種類があります。
◎利用者証明用電子証明書(暗証番号が数字4桁)……インターネットのウェブサイト等にログインする際に利用します(例 マイナポータルへのログイン、コンビニでの住民票の写し等の交付)。「ログインした者が、利用者本人であること」を証明することができます。
◎署名用電子証明書(暗証番号が英数字混在6~16桁)……インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します(例 e-Tax等の電子申請)。「作成・送信した電子文書が、利用者が作成した真正なものであり、利用者が送信したものであること」を証明することができます。
・暗証番号を忘れてしまった場合は、住民票がある市区町村の窓口で暗証番号再設定の手続きが必要となります。
・横浜市民の方の再設定については以下のリンクからご確認ください。
マイナンバーカード(電子証明書)の暗証番号を忘れたりロックした場合はどうすればいいですか?
-
なお、利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)は忘れてしまったが、署名用電子証明書の暗証番号(英数字混在6桁~16桁)は覚えている場合、またはその逆の場合は、コンビニ等のキオスク端末(マルチコピー機)から再設定することも可能です。※リセットアプリのダウンロードが必要です。くわしくは以下のリンクからご確認ください。
マイナンバーカードの暗証番号をコンビニで初期化(外部サイト)(外部サイト)
マイナンバーカードの有効期間は、発行日から10回目の誕生日(未成年者は5回目)まで、電子証明書の有効期間は、年齢問わず発行日から5回目の誕生日までに設定されています。
有効期限を迎える方に対し、有効期限の2~3ヶ月前を目途に有効期限通知書が送付されます。
-
有効期限が切れている場合は、オンライン申請をご利用できません。マイナンバーカードや電子証明書の更新手続きを行った後にご利用いただくか、 郵送または 区役所窓口で申請をしてください。
マイナンバーカードや電子証明書の更新手続きについて(外部サイト)
◎利用者証明用電子証明書(暗証番号が数字4桁)……住所や氏名に変更があっても、有効期限までは引き続きご利用いただけます。
◎署名用電子証明書(暗証番号が英数字混在6~16桁)……住所や氏名の変更に伴い失効してしまいます。引き続きご利用になる場合はお住まいの区の区役所戸籍課登録担当の窓口で、マイナンバーカード表面の記載事項変更と電子証明書の再発行が必要です。
なお、記載事項変更の手続きがお済みの場合に限り、お住まいの区の所管の マイナンバーカード特設センターで電子証明書の再発行が可能です。
以下のサイトをご確認のうえ、本人情報の変更を行ってください。
引っ越ししたため住所が変わりました。住所の変更はどのようにしたらいいでしょうか。(外部サイト)
顔認証マイナンバーカードは暗証番号が使えないため、顔認証マイナンバーカードによる マイナポータルのご利用はできません。
※顔認証マイナンバーカードとは…暗証番号の設定や管理に不安がある方の負担軽減のため、暗証番号の設定を不要とし、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書を用いる際の本人確認方法を顔認証または目視に限定したマイナンバーカードです。
ワードやエクセル形式等でも提出は可能ですが、お使いのソフトウェアやバージョン等により横浜市で確認できない可能性があるため、PDFデータ(できない場合は写真(画像)データ(jpeg,png等))を推奨しています。(【参考】マイナポータルの「よくあるご質問(外部サイト)(外部サイト)」)。
申請について
追加書類は窓口にお持ちいただくほか、不足書類提出フォームより提出することができます。詳細は、障害福祉サービスの申請に係る不足書類提出(横浜市ホームページ)をご確認ください。
オンライン申請時(送信)した日時や申請内容は、パソコンやスマートフォンにダウンロードしたデータの控えで確認できます。送信(申請)したデータの控えは、必ずダウンロードしてください(申請完了ページの「控えをダウンロードする」ボタンから保存できます)。
このページへのお問合せ
健康福祉局障害福祉保健部障害施策推進課
電話:045-671-3601
電話:045-671-3601
ファクス:045-671-3566
メールアドレス:kf-syosystem@city.yokohama.lg.jp
ページID:852-582-723