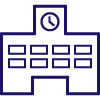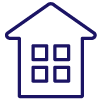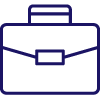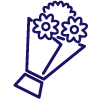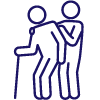ここから本文です。
よくある質問(公園)への回答
最終更新日 2025年1月24日
公園利用のルールについて
他の利用者に十分配慮して遊びましょう!
子どもたちが数人でするキャッチボールなどのボール遊びは、他の利用者と譲り合いながら利用できるという観点から「自由利用」と判断しています。従ってバットや硬いボールを使用するなど、他の人に危険があるような使い方や、十数人で試合をして広い範囲を占用し、他の人が利用できない使い方は認められません。また、ボールが近隣の方の庭に飛び込まないような配慮もお願いします。
公園内では、他の人に怪我をさせる可能性のある行為は禁止されています。
少人数のキャッチボール等他の利用者の迷惑にならず、危険が生じる恐れの無いようなことであれば可能ですが、バット等を使用する本格的な練習や、十数人でおこなう試合などはご遠慮ください。専用施設である野球場をご利用下さい。
公園は地域の憩いの場だけではなく、地域の共通の庭として、地域コミュニティづくりの場としての役割も持っています。公園内でのゲートボール、グランドゴルフは地域の自治会町内会や老人会、公園愛護会の皆さんが行っている場合がほとんどです。また、公園愛護会での清掃活動が終わったあとに行う場合も多くあります。ゲートボールやグランドゴルフは、他の利用者と譲り合いながら利用できるという観点から「自由利用」と判断しています。従って、公園全面を一日中独占して利用したり、子どもたちが利用する遊具のある場所まで範囲を広げるような利用は避けてください。
週末や祝祭日、学校が終わったあとの放課後は公園を利用される方が多くいますので、なるべく平日の午前中など、利用者の少ない時間帯に行いましょう。
利用する範囲を公園全面にせず、他の利用者が十分に利用できるスペースを確保しましょう。特に、子どもたちが利用する遊具のある場所まで範囲を広げるような利用は避けましょう。
他の利用者がプレーしている場所を横切らざるを得ない場合、一時的にプレーを中断し、渡りきるまで待ってあげましょう。
自治会町内会、公園愛護会、老人会などで行う場合は、使う曜日を決め、その結果を回覧板や公園内に掲示するなどして、他の利用者への周知をしましょう。
他の利用者に配慮して行っている場合でも、他の利用者が「あの人たちは公園を独占している」と思われることがあり、土木事務所に苦情が来ることがあります。出来る範囲で、他の利用者にも挨拶などの声かけをすることにより、良好なコミュニケーションを図りましょう。
公園は自転車などの車両の乗り入れは原則としてできませんが、子どもが自転車の練習をしたり、自転車で公園を通るときには、他の利用者に注意して、必要に応じて自転車を降りたりするなど、十分注意してください。
飼い犬は、横浜市動物の愛護及び管理に関する条例で係留(つなぐこと)しておくことと決められています。公園においても例外ではなく、犬を放すことはできません。最近は、犬を放すことに関する苦情も多く寄せられており、看板などで注意を促していますが、地域の皆さんでも、お互いに注意しあっていただきたいと思います。
他人の迷惑となるルアーなどの投げ釣りは禁止しています。他の利用者に迷惑のかからない範囲で釣りをなさってください。ただし、生物の保護のため、釣りを禁止している公園もあります。池の水質や生き物に影響があるため、えさ、釣り針、糸を放置しないようにお願いします。
公園内のどんぐりなどの木の実は、落ちているものであれば拾って持ち帰っても構いません。ただし、他の人が拾っている場合には譲り合う、業務・商売用などで大量に持ち帰らない、木になっている実を枝のままとらないなどのご配慮をお願いします。また、梅や柿などの果実や竹の子は、お持ち帰りは禁止されています。無許可で採集すると罰せられることもあります。
自分で飼える数にとどめる、捕まえた後、放してあげるなどの配慮をお願いいたします。子ども達が健全に育つためにも、昆虫や魚などに接する機会を作ることが大切です。公園内でトンボやクワガタ、ザリガニなどをとることもその機会であるといえます。一方で、ホタルやサワガニなど貴重な動植物が生息している公園もあります。公園内で虫などを大量に採取することや、貴重な動植物を採取することは禁止されています。
市販の子ども用花火などは可能ですが、ロケット花火をはじめとする打ち上げ花火やバクチクなど、他人に危害が及ぶ可能性のあるものはご遠慮ください。また、花火をしながら騒いだり、ゴミを散らかしたりすると、近隣や他の利用者に迷惑ですので、ご注意ください。
公園では専用のバーベキュー場以外の場所で、個人的に火気を使用して焼き芋やバーベキューを行うことは原則としてできません。市内数公園にバーベキュー場を設置していますので、ご利用ください。(有料・要予約)
公園では、個人や法人での物品の販売は原則としてできません。ただし、フリーマーケットは資源の再利用を促す側面があることから、自治会、町内会、公園愛護会などの団体(注1)が「地域の行事」として行う場合に限り、開催することができます。その場合は、地域に広く周知することと、事前に土木事務所(電話045-531-7361)への申請が必要になります。また、出店、参加の際には公園周辺に無断駐車のないよう主催者として配慮をお願いします。
(注1)自治会・町内会に関係する子供会、婦人会老人会並びにマンション管理組合などを含みます。企業や個人の集まりのみでフリーマーケットを開催することはできません。
公園は地域のみんなのものです。皆さんで譲り合って、楽しくご利用ください。運動会などの催しについて、許可することがありますが、それ以外の場合は公園を利用する人同士で声を掛け合い、ゆずりあいながら利用しましょう。
子供たちがルールを守って楽しく安全に遊べるように、次のポイントに配慮しながら保護者の方で見守ってくださるようお願いします。
子供たちの服装に注意してあげてください。
マフラーやカバン、ランドセル、ひも付き手袋などを身に付けて遊ばない。
ひっかかりやすく、ぬげやすい服はやめ、遊びやすい服を身に付ける。
遊具の無理な使い方はやめましょう。
反対側から利用しない。手を放したり、飛び降りたりしない。友達と押し合わない。
ブランコは、二人で乗ったり、立ってこがない。
3歳から12歳が主な対象です。公園では、低年齢の子どもの遊ぶ場所と、活発に子どもが運動する場所を分けて配置しています。遊具も子どもの運動量や運動能力に合わせた様々な遊具を設置しており、今後順次、対象年齢を表示していく予定です。未就学児については、保護者の方が必ず付き添って利用してください。
砂場の衛生状態については、毎年、市内数十箇所の公園で砂場の衛生検査を実施しており、「砂場で遊んだ後に手を洗えば大丈夫」という結果にはなっています。なお、猫のフン等の対策として、公園愛護会や利用者の皆さんに管理等のご協力をいただける場合、砂場へのネット掛けなどを実施することもできます。
公園の水道は手を洗ったり、子どもが砂場遊びで利用するなど、みんなで使うためのものです。個人で独占して使用することは原則としてできません。保育園や子育てサークルなど、特定のメンバーで構成する団体などの場合も同様です。
公園の維持管理について
公園愛護会がある身近な公園では、公園愛護会に日常の清掃、除草のご協力をいただいています。大規模な公園では、園路・広場等を中心に、年に1-2回草刈を実施しています。
公園の木は、樹木の健全な生育を図る目的で、木の種類にもよりますが複数年に1回程度、剪定を実施しています。また、枝が隣接の民家に越境している場合や、枝葉が茂りすぎて公園内の見通しが悪い場合などには、優先的に枝を切っています。その公園を管理している土木事務所(電話045-531-7361)に連絡をいただければ、状況を確認し、必要に応じて枝を切るなどの対応をいたします。ただし、木の枝を切ることに対しては、地元住民の間でも賛否両論がでることが多いため、切る程度については調整が必要です。
公園の木は、地域の方にとっての貴重な緑です。このため、伐採することは望ましくありませんが、公園ができてから年数が経ち、木が成長して間隔が込み過ぎることにより、公園が暗くて見通しが悪くなり、防犯上の問題等が生じている場合もあります。このような場合、公園愛護会や町内会等、地域の皆様とご相談しながら、一部の木の伐採を行う場合もあります。
公園の木の落ち葉については、近隣の方には特にご迷惑をおかけしていますが、市民の皆さんの財産である公園の緑を守り、育てていくため、ご理解・ご協力をお願いします。なお、落ち葉が落ちる・日陰になる・BSが映らない等の理由での樹木の剪定は行っていませんが、枝が越境している場合は、所管の土木事務所(電話045-531-7361)にご連絡いただければ、状況を確認し、必要に応じて枝を切るなどの対応をいたします。
人体に危害を加える害虫が発生した場合、必要に応じて害虫のついている枝を取り除いたり、薬剤を注入または散布して害虫を駆除しています。一方で、「自然の一部」として、一定数の虫は必ず公園内にいるものです。人体へ危害を加えない虫については、周辺環境、利用者の健康に配慮し、公園などの公共施設においては極力薬剤を使用しないようにしておりますので、ご理解ご協力をお願いいたします。
ごみ箱については、遠方からの利用者が想定される公園の他、地域からごみ箱の設置要望があり、かつ、管理をしていただける場合に設置してきました。しかし、公園内の美化の推進やゴミの減量化の推進が近年、大きな課題となってきたため、公園内のごみ箱の取り扱いについて検討したところ、アンケート調査等の結果から、過半数の方が撤去を望むという結果が得られました。そこで、平成15年9月1日以降「公園でのごみは持ち帰る」ことをお願いして、身近な公園のごみ箱を原則として撤去することとしました。ご理解ご協力をお願いします。
横浜市の公園では、猫のフンなどで汚れがひどい場合やガラスなどの危険物が入っている場合は、現場を確認の上、それらの異物を除去したり、砂が減っている場合には砂の補充を行っていますが、砂の消毒等は行っていません。また、利用者の方にもフンを取り除いていただくなど、ご協力をお願いいたします。
現地を確認・調査し、ケガ等危険性のある場合は早急に応急処置・修理を行いますので、土木事務所(電話045-531-7361)にご連絡ください。また、明らかにケガをする危険性のある遊具については、土木事務所職員が現地にかけつける前であっても「使用禁止」等の張り紙を表示していただくと助かります。
横浜市では、雲のない夜に満月が照らす地面の明るさを基準に、身近な公園500m2あたり100W水銀灯1灯、1000m2あたり200W水銀灯1灯の基準で照明灯を設置しています。公園が暗く感じる場合には、照明灯設置後何年も経過し、水銀灯の寿命によって照明灯の明るさが低下した場合や、樹木の成長によってできる影によることがあります。現地調査を行い、その結果に基づき対応をいたしますので、土木事務所(電話045-531-7361)までご連絡ください。
公園愛護会がある身近な公園では、公園愛護会に日常の清掃を行っていただいています。また、観光公園など大規模な公園では、原則として市が清掃を行っています。
公園や街路樹から発生する剪定枝等の再資源化を図るため、横浜動物の森公園内に「緑のリサイクルプラント」を平成18年3月から稼働開始しました。
この施設は、公園や街路樹から発生する剪定枝や刈草等をチップ化や堆肥化して再利用するもので、チップは雑草の発生を抑えるためのマルチング材として、堆肥は土壌改良材として公園整備などに利用するほか一般販売も行っています。
公園の花壇は、公園管理者である横浜市の許可なくつくることは出来ません。
地域の皆様で結成され、公園を管理するボランティア団体である公園愛護会が、公園管理者である横浜市と協働で花壇を設置している公園もあります。
公園愛護会活動の一環として花壇をつくりたい場合は、港北土木事務所にご相談ください。
遠くからの利用者が多い公園や、野球場等、長い時間滞在する施設がある公園など、トイレの必要性が高い公園には設置していますが、その他の身近な公園では、利用マナーによるトラブルの原因になることも多いため、基本的には設置していません。ただし、周辺にお住まいの方々のご理解が得られること、一定の面積があることなどの条件が整えば、設置することも可能です。
地域からの要望があり、利用者も多く、設置効果が高いと思われる公園から順次、設置しています。
遊具には、幼児向けや小学生向け等、対象年齢や種類により様々なものがあります。また、遊具を設置する場合、安全確保のため周囲にスペースが必要なため、遊具の設置により広場が狭くなってしまう等、公園の利用状況がかわる場合があります。土木事務所(電話045-531-7361)にご相談いただくとともに、公園愛護会や町内会等、公園を利用されている地域の皆様でお話し合い下さいますようお願いします。
公園の愛護会について
- 地域の方々の共同の「庭」であり、市民の共有の財産である身近な公園の管理にあたっては、公園を設置している横浜市だけでなく、地域の方々の積極的なご協力が必要です。このため、公園の清掃・除草等の日常的な管理について、地域の方々を中心にボランティアの団体を結成し、ご協力いただいています。これが「公園愛護会」です。
- 「公園愛護会」(みどり環境局のページへ)
公園の清掃・除草や、樹木への水やり、公園利用者へのマナーの呼びかけなどを行っています。中には、公園の特徴を活かして、花壇を作って地域のみなさまの目を楽しませたり、樹林地の保全に取り組んでいる愛護会もあります。
公園の周辺にお住まいの地域の方々がメンバーです。町内会の役員や、老人会・子ども会などが愛護会のメンバーとなっているところもあります。

港北土木事務所のキャラクター「どぼくねこ」
このページへのお問合せ
ページID:204-791-025